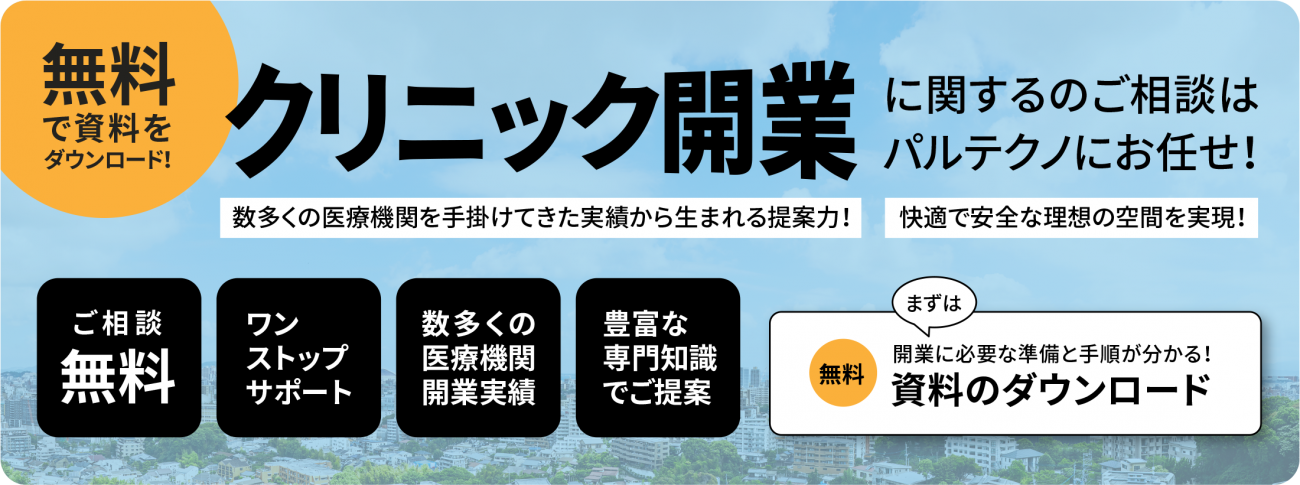院内処方とは?院外処方との違いやメリット・デメリット、注意点を解説
診察後の薬の提供方法は、経営や業務フローに関わる重要なポイントであり、クリニックの開業時に検討が必要です。現在は院外処方が主流となっていますが、今でも一部のクリニックでは「院内処方」を採用しています。
今回の記事では、院内処方のメリットとデメリット、院外処方との違いについて詳しく解説します。開業の際に最適な方法を選択する上での参考にしてください。
院内処方とは?院外処方との違い
患者が処方された薬を受け取る方法には「院内処方」と「院外処方」の2つの種類があります。「院内処方」とは、診察を受けたクリニックで薬が用意され、その場で薬を受け取ることができる方法です。
一方で、「院外処方」は診察を受けたクリニックで発行された処方箋を、患者が調剤薬局に持って行き、そこで薬を受け取る方法のことをいいます。
院内処方が少なくなった背景
現在多くのクリニックで採用されているのは院外処方であり、院内処方の件数は年々少なくなっています。院内処方の割合は、約40年前は約90%でしたが、現在は約20%にまで減少しました。
(参照:日本薬剤師会「医薬分業進捗状況(保険調剤の動向)」)
減少した要因として考えられることを2つ解説します。
医薬分業の推進で院外処方が大幅に増加
多くのクリニックが院内処方から院外処方へと切り替えた大きな理由として、医薬分業の推進があげられます。
医薬分業とは、医師が患者に処方箋を交付し、薬剤師がその処方箋に基づき調剤を行うことです。医師と薬剤師がそれぞれの専門分野で業務を分担することによって、医療の質の向上を目指します。
医薬分業によって、次のようなことが期待できます。
|
・医師は使用したい薬が手元になくても処方でき、処方薬の選択肢が広がる ・医師と薬剤師のダブルチェックによる安全性向上が期待できる ・処方箋を患者に交付することで、服用する薬の理解を深められる |
1997年に厚生労働省が37のモデル国立病院に対して完全分業(院外処方箋受取率70%以上)を指示して以降、医薬分業は急速に進み、2003年に初めて全国の処方箋受け取り率が50%を超えました。
(参照:厚生労働省「薬局・薬剤師のあり方、医薬分業のあり方(その2)」、日本薬剤師会「医薬分業とは」)
院内処方によるメリットが減少
院内処方では、薬価差益(患者が払う薬代と薬の仕入れ値の差額)によってクリニックが利益を得られる可能性があります。
しかし、近年の薬価引下げやジェネリック医薬品の普及拡大で利益を出しづらくなっており、こうした現状が院内処方が減っている要因のひとつであるといえるでしょう。
院内処方のメリット

解説したとおり、院内処方の件数は年々減少していますが、クリニック・患者双方にとってのメリットもあります。それぞれ順番に解説します。
薬の変更や追加、日数調整がしやすい
処方内容に変更が必要となった場合でも、移動せずにクリニックで対応が可能です。
また、調剤薬局への個別の連絡等が不要なため、外部とのやりとりに要する業務負担が少ないといえます。
医師や看護師、薬剤師など他職種との連携がとりやすい
院内に薬剤師が常駐していることで、医師・看護師とのリアルタイムな処方相談が可能になり、在庫状況の即時確認や薬剤適正使用の提案もその場で受けられます。
また、チーム医療体制により責任分担が明確になるため、患者ごとに最適な処方を迅速に決定できる環境が整えやすくなります。
薬局に行く手間が省ける
院内処方の場合、診察終了後にその場で薬が受け取れます。薬局まで薬を受け取りにいく手間を省けるため、患者にとっての時間的・身体的負担が少ないことがメリットです。
特に高齢者や子ども連れの患者にとっては、診察後に薬局へ足を運ぶ必要がなく、身体的・時間的負担の軽減につながります。また、診察後に一度の会計でまとめられる利便性の高さも特徴です。
院内処方のデメリット
院内処方は、メリットだけではなく、クリニック・患者にとってのデメリットになる場合もあります。ここではそれぞれの内容を確認していきましょう。
薬剤師の人件費などのコストがかかる
院内処方で算定可能な「処方料」の点数は、院外処方の「処方箋料」に比べて低く設定されており、1回の処方で得られる利益は院内処方の方が少なくなる可能性があります。
また院内処方の場合は、薬剤師の人件費、調剤機器の管理費、薬の在庫費用がかかるため、コスト面での負担が院外処方に比べて大きくなる傾向にあります。クリニックにて薬を用意するにあたり、余剰在庫となった場合は赤字のリスクもあるため、在庫管理の徹底が必要です。
薬を管理するためのスペースを確保する必要がある
クリニックで調剤を行ったり、薬剤を保管したりするためのスペースを確保しなければならないため、小規模なクリニックの場合は難しい場合もあるでしょう。
その場合は、クリニックの設計段階からコストを考慮した上で院内処方の実施を検討する必要があります。
当社では、クリニック企画から施工、アフターケアまで自社で一貫したサービスを提供しております。また、資金調達や事業計画策定のサポートも対応可能です。医療施設、福祉施設、クリニック、調剤薬局の設計・施工をご検討中の方はぜひ当社までご連絡ください。
薬局でのダブルチェックが受けられない
院内処方では、医師による処方と薬剤師による調剤のそれぞれが独立していない場合があります。特に薬剤師のいないクリニックでは、医師の処方がそのまま調剤されるため、ミスがあった場合も見逃されてしまうリスクが考えられます。
薬剤師による服薬指導が実施されないことに不安を感じる患者へのケアや、複数のクリニックにかかっている患者の薬の飲み合わせ・重複投薬のチェック等、安全に薬を提供できる体制を整えることが大切です。
薬の選択肢が限定される場合がある
調剤薬局では、さまざまなクリニックの処方箋に対応するため、豊富な種類の薬を常備しています。そのため、患者の希望に応じて先発・後発医薬品を選択可能なことが一般的です。一方、院内処方では在庫の種類が限られることで患者の希望通りに調剤ができない場合があります。
院外処方を実施する上での留意点

院内処方のメリット・デメリットを理解した上で、院外処方の採用を検討する場合は、以下のことを理解しておく必要があります。
近隣薬局との関係構築・連携が重要
院外処方の場合、患者はクリニックで処方箋を受け取ると、そのまま近隣の薬局に持参することが多いです。そのため、近隣薬局とは開業の際やその後も継続的に良好な関係を築いていくことで、連携がスムーズにとれるようになるでしょう。
近隣薬局との関係構築は、患者が安心して院外でも薬を受け取るができる環境づくりにもつながります。
薬局の在庫を考慮した処方が必要な場合がある
院外処方の場合は、処方した薬が薬局に常備されていない可能性を考慮する必要があります。たとえ処方をしたとしても、薬が薬局で在庫されていない場合、治療の開始が遅れることにもなりかねません。
近隣の薬局と事前に薬の取り扱いについて相談をするなど、連携を深めていくことで、患者がスムーズに薬を受け取ることができるでしょう。
院内・院外処方の併用制限
同じ患者に対して、同一診療日に院内処方と院外処方を併用することは原則できません。
緊急事態の場合は、認められるケースもありますが、その際は保険請求を行うために、レセプト上に適切な記録を残す必要があります。ただし、別日であれば院内処方と院外処方の併用は問題ありません。
院内処方の条件と違法となるリスク
院内処方は、薬剤師がいないクリニックでも実施は可能ですが、条件があります。医師自身が「調剤」(薬の選別・混合・分包など)を行い、そのまま患者に投薬する場合に限り、合法とされています。
つまり、医師以外(看護師や事務スタッフ)が調剤行為を行うことは「無資格調剤」となり、薬剤師法第19条違反となるため厳禁です。(出典:薬剤師法|第19条)
院内処方を行う場合には、医師自らが調剤・投薬を行う体制を取る、もしくは薬剤師を配置し、条件を満たした上で実施しましょう。
クリニック・患者双方のメリットを理解して院内処方と院外処方を選択しよう
院内処方と院外処方は、患者・クリニックの双方にとってさまざまなメリットとデメリットが存在します。開業を予定しているクリニックの規模や地域の状況、患者層などによって最適な選択は異なります。
院内処方を導入するかどうかは、コスト面や業務負担、患者にとっての利便性などを総合的に検討した上で判断するとよいでしょう。
当社では、クリニック企画から施工、アフターケアまで自社で一貫したサービスを提供しております。また、資金調達や事業計画策定のサポートも対応可能です。医療施設、福祉施設、クリニック、調剤薬局の設計・施工をご検討中の方はぜひ当社までご連絡ください。
また、開業に必要な資金の目安や具体的な手続きについては、以下の記事もぜひご覧ください。
クリニック開業に必要な資金は?診療科目別の目安と必要な手続きを解説